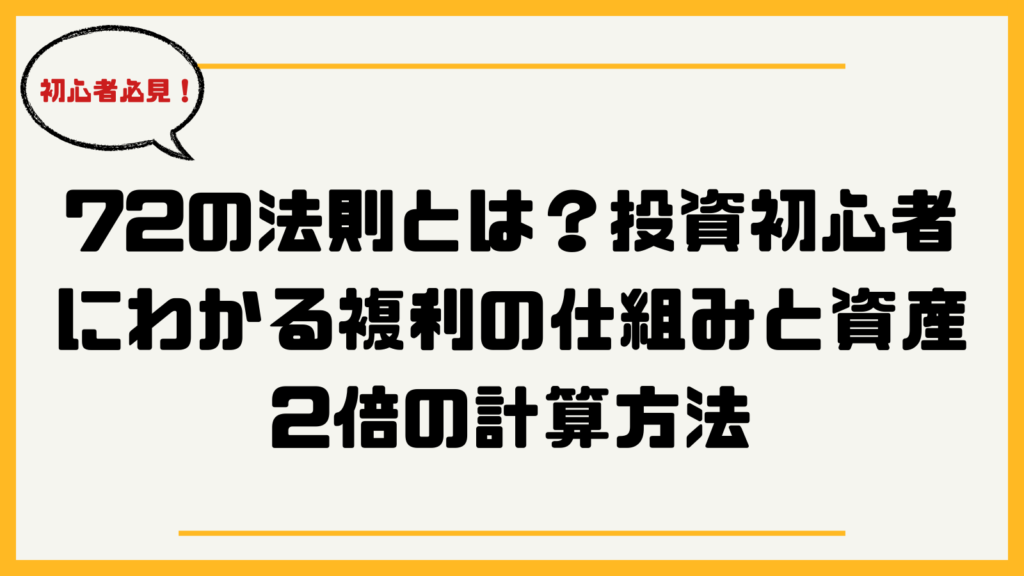
「72の法則」って聞いたことありますか?
TBS系ドラマ「御上先生」でも取り上げられ、話題になっていましたね。
これは、金利からお金がどれくらいで2倍になるかを簡単に知れる、とても便利な考え方です。
複利と関係があるので、投資初心者でも資産が増えるイメージをつかみやすくなります。
この記事では、72の法則の基本や計算の仕方、なぜ成り立つのかをわかりやすく紹介します。
さらに、115の法則や126の法則との違いや、積立投資やNISAでの活かし方、メリットや注意点まで、初心者向けにやさしくまとめました。
72の法則とは?投資初心者にもわかりやすく解説
72の法則の基本的な意味
72の法則とは、お金がどれくらいの期間で2倍になるかを簡単に知ることができる投資の法則です。
数字の「72」を使って、複利と金利の関係からサッと計算できるので、証券や積立投資を考えるときにとても便利です。
この法則を知っておくと、お金の増え方をすぐにイメージでき、資産運用の計画にも役立ちます。
さらに、72の法則は115や126の法則ともつながっていて、資産が3倍や4倍になる期間も考えられます。
初心者でも複利の力を理解するための知恵として覚えておくと安心です。
「お金が2倍になる期間」を簡単に求められる仕組み
やり方はとてもシンプルで、「72」を利率で割るだけです。
例えば、年利6%なら72÷6で、約12年でお金が2倍になることがわかります。
この仕組みは複利の効果を前提にしていて、投資や積立を考えるときにすぐ役立ちます。
数字を見ただけで将来の資産イメージをつかめるので、初心者でも資産計画が立てやすくなる便利な方法です。
なぜ72という数字が使われるのか
「72の法則」で出てくる数字「72」は、ただの偶然ではなく、数学的な裏付けと日常で使いやすい便利さの両方から選ばれたものなんです。
少し難しい話になりますが、本来、資産が複利で増えて2倍になるまでの時間は「69.3 ÷ 利回り」で表されます。
これは「自然対数(ln)」という数学の考え方が関係していて、正確には「ln(2) ÷ 利回り」で計算するからです。
ln(2)の値が約0.693なので「69.3」が正しい数値になります。ですが、69.3は暗算には少し使いにくい数字ですよね。そこで「70」を使う方法もありました。
ではなぜ「72」が定着したのかというと、答えはとてもシンプルで「割り算しやすいから」です。
72は2、3、4、6、8、9、12といった多くの数字で割り切れるので、頭の中でサッと計算できます。
たとえば利回り6%なら「72 ÷ 6 = 12年」、8%なら「72 ÷ 8 = 9年」とすぐに答えが出せます。これが69や70だと割り切れず、計算がややこしくなってしまうんです。
また、72は投資やお金の教育をする場でもとても説明しやすい数字でした。「この利回りなら何年でお金が2倍になるか」が直感的に伝わるので、学びの場で広く使われ、世界中に広まったのです。
初心者が知っておくべき注意点
72の法則は便利ですが、いくつか注意点があります。
まず、あくまで目安であって、必ずしも正確にお金が2倍になるわけではありません。
金利は変動することもありますし、税金や手数料も考慮する必要があります。
また、低金利やインフレの影響で計算通りにならないこともあります。
それでも、法則自体を知っておくと、お金が増えるイメージをつかみやすくなり、投資を始めるときの判断や計画に役立ちます。
72の法則の計算方法と数式
計算式の基本(72 ÷ 金利 = 2倍になる年数)
先ほどもお話しした通り、72の法則の計算はとてもシンプルです。
お金が2倍になるまでの年数は、「72を金利で割るだけ」でわかります。
たとえば、年利6%なら72÷6で、約12年でお金が2倍になるというイメージです。
手元に100万円あったとします。
そのお金をNISAなどで運用をして、年利6%で運用ができれば12年後には200万円になっているということですね。
年利3%なら72÷3で約24年。
数字を当てはめるだけなので、難しい計算や数式を知らなくても、将来の資産がどれくらいで増えるかを簡単にイメージできます。
複利での計算と単利の場合の違い
お金の増え方には「単利」と「複利」があります。
単利は元本にだけ利息がつく計算で、毎年同じ金額ずつ増えるイメージです。
一方、複利は利息にもさらに利息がつくので、時間が経つほどお金がどんどん増えていきます。
72の法則は複利を前提にしているので、単利とは結果が大きく違います。
たとえば年利5%で複利なら約14年で2倍になりますが、単利だと20年以上かかる計算になります。
複利の力を知ると、長期投資のメリットがよくわかります。
72の法則と関連する115の法則・126の法則
115の法則・126の法則とは
115の法則と126の法則は、資産が3倍や4倍になるまでの期間をざっくり知るための目安です。
72の法則が「お金が2倍になる期間」を教えてくれるのに対し、115は3倍、126は4倍と、さらに長期の資産成長をイメージできます。
計算方法もシンプルで、金利でそれぞれ115や126を割るだけです。
たとえば年利5%なら115÷5で約23年、126÷5で約25年といった具合です。
72の法則との違いと使い分け方
72の法則はお金が2倍になる目安、115の法則は3倍、126の法則は4倍になる目安と、それぞれ対象が違うだけで考え方は同じです。
使い分けのポイントは、どれくらいの期間で資産を増やしたいかによって選ぶことです。
短期~中期の目安なら72の法則、もう少し長期の目安を知りたいときは115や126の法則を使うとわかりやすくなります。
積立投資・NISAと72の法則の関係
積立投資で72の法則をどう活かすか
積立投資では、少額でも毎月コツコツお金を入れていくことで、複利の力を活かして資産を大きく育てることができます。
例えば毎月3万円を年利5%で20年間積み立てると、元本は720万円ですが、複利の効果でお金は約1,400万円ほどに増えます。
年利6%ならさらに約1,600万円まで膨らむイメージです。
積立期間を延ばせば、資産はさらに大きく増え、25年間であれば年利5%でも約1,900万円、年利6%なら約2,200万円に達します。
これを知ることで、「少額でも時間をかければ大きな成果が期待できる」ということが直感的に理解できます。
証券投資の世界では、72の法則を使って資産が倍になる期間をざっくり計算することもできます。
例えば年利6%なら、72 ÷ 6=12年でお金が2倍になる、と見積もれます。
これを積立投資に当てはめると、「20年続ければどのくらい増えるか」を直感的にイメージでき、投資の計画やモチベーションに役立ちます。
さらに、3倍・4倍になる目安には115の法則や126の法則もあり、これも簡単な計算で将来の資産イメージを知る知恵として活用できます。
毎月の積立額や期間、利回りの組み合わせを意識するだけで、投資初心者でも複利の力を味方にしてお金を育てる感覚がつかめます。
即時に大きな成果は出ませんが、長く続けることで資産形成の楽しさを実感できるのが積立投資の魅力です。
その目安として72の法則は役に立つと思います。
投資初心者が72の法則を学ぶ意義
なぜ投資を始める前に知っておくべきか
投資を始める前に72の法則を知っておくと、資産形成のイメージがぐっとつかみやすくなります。
複雑な数式や難しい証券用語を知らなくても、資産の増え方を直感的に理解することができるので、将来どのくらい資産が増えるかを即時にイメージできます。
また、投資初心者にとって、この知識はただの計算のコツではなく、「時間を味方につける投資」を理解する入り口にもなります。
少額からでも毎月コツコツ積み立てることで、複利の力が徐々に効いてくることを知れば、長期的な資産形成のモチベーションも自然と高まります。
投資の基本的な感覚として「お金は時間をかけるほど増える」という理解を持っておくと、リスクへの不安も少なくなり、計画的に投資を続けやすくなります。
まとめ
投資はどうしても数字や専門用語が多くて難しく感じがちですが、「72の法則」のようなシンプルな知恵を知っておくだけで、一気に未来のお金のイメージがしやすくなります。
数字に強くなくても、「このくらいの利回りなら何年で倍になるんだ」と直感的に分かるのは心強いですよね。
投資の世界は短期的に上がったり下がったりしますが、長い時間を味方につければ着実に成果が見えてきます。
だからこそ、焦らずコツコツと積み立てを続けることが大切です。
これから投資を始める人にとって、「72の法則」は将来のお金を考えるうえでの小さな羅針盤のような存在になります。
このシンプルな考え方を味方にしながら、自分らしい資産づくりの一歩を踏み出してみてください。





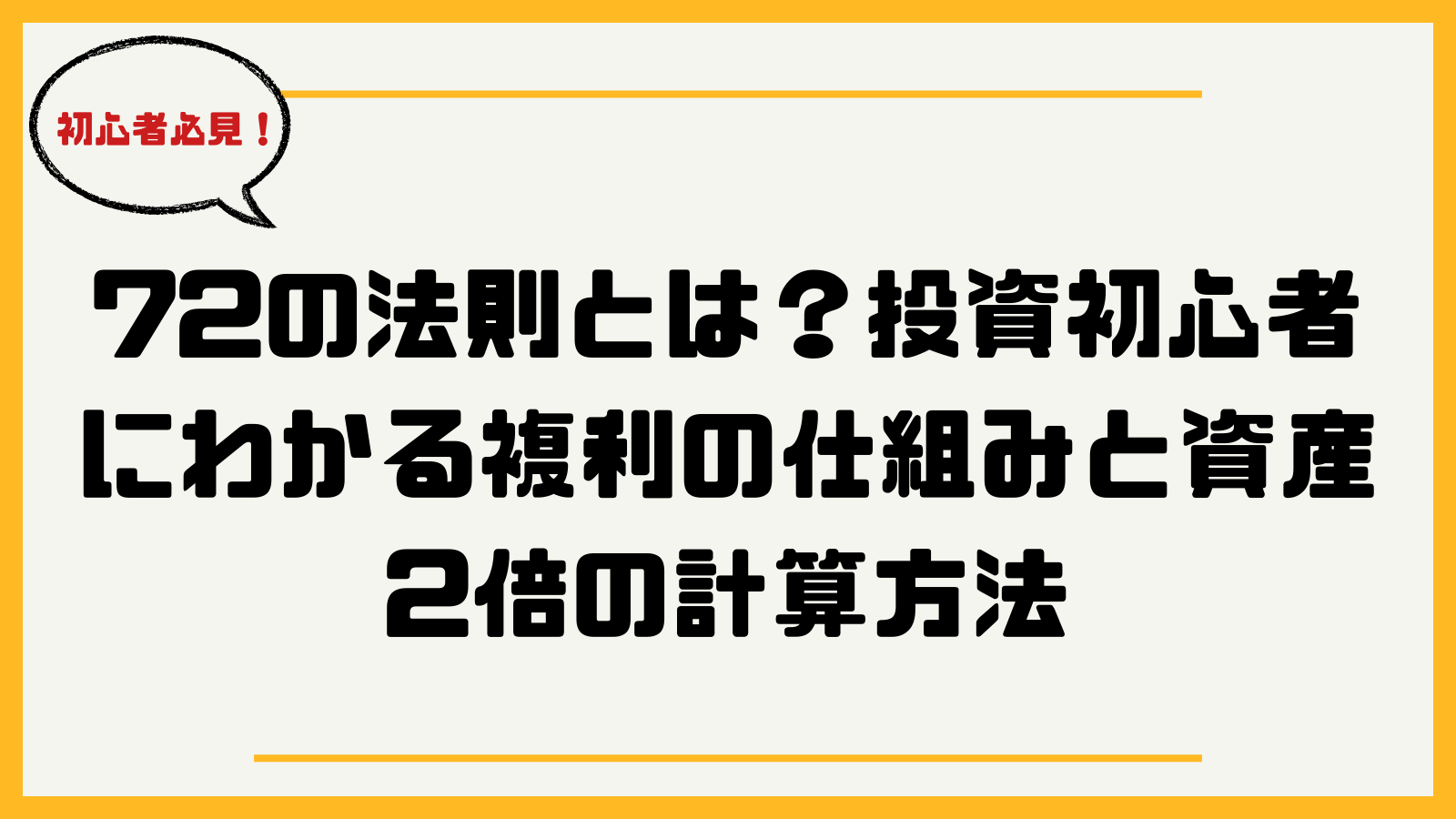


コメント