
突然ですが、
投資の終わらせ方について知っていますか?
新NISAが始まり、投資を始めた方が増えてきましたね。
私もそのうちの1人ですが、投資について勉強していく中でとても興味深かったのが、
【4%のルール】です。
いざ始めてみたものの、最後はどのように終わらせるのかを知らない方も多いかと思います。
「最後は全部引き出して終わりでしょ?」と私も考えていましたが、実は違うようです。
この4%のルールに基づいて運用をすれば、
【お金を引き出しながら、資産を増やし続けることができる】
ということです。
「そんなうまい話あるの?」と思うかもしれませんが、
だれでも実践できる方法ですので、ぜひ読んでみてください。
4%のルールとは?
4%のルールとは、1998年にアメリカのトリニティ大学のグループによって発表された論文で、別名「トリニティスタディ」と呼ばれています。
要約すると、
年間支出の25倍の資産があれば、毎年4%の切り崩しをしても資産が尽きることなく運用し続けることができる。しかも、30年後に資産が残っている確率は95%もある。
という内容です。
例えば、年間の生活費が300万円の場合は、7,500万円あれば働かずとも生活ができてしまうというわけです。
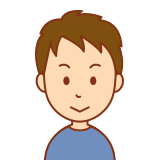
いや、毎年4%の切り崩しをしたら25年で0になるでしょ?
と、普通に考えるとそうなのですが、4%のルールに沿って運用し続けると、
25年後以上資産が長持ちし、しかも、
多くの場合で資産が8倍に成長する。
ということがこのトリニティスタディという研究でわかったそうです。
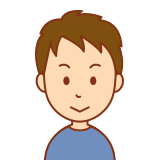
そもそも7,500万円なんて私には無理なので関係ない話だな。。。
と、私も考えていましたが、NISAについて少し知識がつくと、
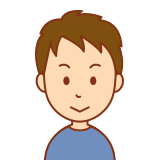
なんか、不可能でもないかも。。。
と、思えるようになるかもしれません。
時間をかけてお金に働いてもらいながら、【長期・積み立て・分散】を続けていれば実は多くの方が実現できるのです。
今回の記事は4%のルールについて解説していますのでNISAについては省きますが、
NISAに興味がある方は、下記の記事もぜひ読んでみてください。
なるべく簡単にざっくりとNISAについてまとめています。
また、NISAを始めたほうが良いことはわかっているけど、なにから始めればいいの?
という方は、まず口座開設から始めてください。画像付きで解説しています。
前提条件
4%の資産を切り崩しながら運用を続けるためには、下記の前提条件があります。
ポートフォリオを株式50%:債券50%にする。
ポートフォリオとは、保有する金融資産の組み合わせのことをいいます。
この資産配分を株式50%:債券50%にしなければいけないのですね。
なぜなのか?
結論から話すと、
1つの資産に集中するとリスクが高いため、異なる資産を組み合わせてリスク分散を行うため。
もう少し理解を深めるために、株式と債券について簡単にまとめます。
【株式】
・企業の成長に応じて資産が増える可能性がある。
・価格変動が大きく、リスクも高い。
・例:日本株、米国株、新興国株、インデックスファンドなど
【債券】
・定期的な利息収入が得られ、安定性が高い
・株式よりリスクが低いが、リターンも控えめ
・例:国債、社債、債券ETFなど
要するに、資産が増える可能性があるがリスクも高い、言わば攻撃型な株式と、大きく資産は増えないがリスクが低く安定性のある債券という防御型をバランスよく組み合わせることで資産を減らすことなく運用し続けていけるということなんですね。
4%のルール3つの注意点
未来の市場環境では通用しない可能性がある
4%のルールは、過去のデータを基にしたものであり、将来の市場環境でも必ず通用するとは限りません。投資の未来予測は誰にもできないので当然と言えば当然のことですね。
通用しない可能性としては、
・市場リターンの低下:今後、株式市場の成長率が鈍化すると、4%の引き出しでは資産が減る可能性がある。
・インフレの影響:物価上昇(インフレ)が激しくなると、想定よりも早く資産が目減りする。
などが考えられます。
【対策】
・市場環境に応じて柔軟に引き出し率を調整する。(4%➡3%)
ちなみに引き出し率を4%ではなく、3%にすると30年後に資産が残る可能性はなんと100%になります。
たかが1%と思うかもしれませんが、7,500万円で考えたときの1%は75万円。
生活水準を落としても問題ないという方にはおすすめの対策です。
初期の市場暴落に弱い
取り崩し開始直後に市場が暴落すると、資産が想定よりも早く減少するリスクがあります。
暴落が予測できる人もまずいません。リーマンショックやコロナショックのような暴落が取り崩し開始直後にきてしまう可能性は0ではないので、こちらも対策が必要です。
【対策】
暴落時を乗り切るための生活費を現金で用意しておく。(2~5年分)
こればかりは自身で働いて事前に準備をしておくしかありません。
資産の取り崩しは、ほとんどの方が定年を迎えた後に行うかと思いますので、退職までの間に計画的に準備を進めることが大切です。
すべての国・市場で適用できるわけではない
4%のルールは、米国市場のデータ(主にS&P500の過去リターン)をもとに考えられたものです。
しかし、他の国や市場では、必ずしも同じルールが適用できるとは限りません。
国ごとに市場の成長率が異なったり、通貨のリスクがあるなど要因は様々です。
【対策】
全世界株式(オルカン)などの分散投資に優れた株式に投資する。
名前の通り全世界の株式に投資をする通称オルカン。
全世界とはいえ、実際のところは米国株式の比率が6割ほどとなっていますが、S&P500などの1つの国に集中したものに比べると断然リスク分散に効果的かと思います。
オルカンについてもう少し深く知りたい方は下記の記事も読んでみてください。
まとめ
今回は4%のルールについて話してきましたが、まとめると下記のようになります。
・4%のルールは「資産を守りながら取り崩す」ための考え方
・NISAを活用すれば、税金の負担を減らしながら資産を増やせる
・長期的に運用し、無理のない投資を続けることが重要
資産運用を始めたばかりの私たちには、まだまだ先の話にはなりそうですが、
4%のルールを知っておくだけで、老後にどのくらいお金が必要なのかを
把握しやすくなると思います。
金融庁などが出している、資産シミュレーターなどを使って自身の将来に必要なお金を見ておくのも良いかもしれませんね。
もっと、お金について知りたいと思ってくれた方は本を読んで学ぶことをおすすめします。
私が読んでタメになった本のレビューもありますので、
気になった方はぜひ読んでみてください。






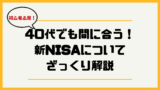
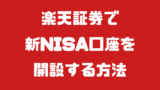
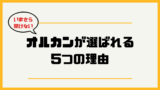
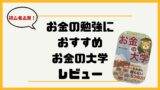
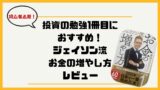
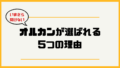
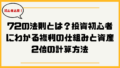
コメント